眼精疲労の対策|メガネ・コンタクト・セルフケア・薬でできる予防と解消法

眼精疲労を予防するためには、まず目を過度に使いすぎないことが基本です。
特にパソコンやスマートフォンを長時間使用する際は、作業方法や環境を工夫し、意識的に目を休める時間を確保しましょう。
また、目の乾燥を防ぐことや、ストレスを溜めないようにすることも眼精疲労の対策として有効です。
この記事では、眼精疲労の原因から、すぐに実践できる具体的な予防・解消法までを網羅的に解説します。
この記事の目次
眼精疲労とは?ただの目の疲れとは異なる症状と原因

眼精疲労は、単なる目の疲れとは異なり、その原因は多岐にわたります。
パソコンやスマートフォンなどの画面を長時間見続けることによる目の酷使はもちろん、同じ姿勢での作業や、まぶしすぎる照明、エアコンの風が直接目に当たるといった環境要因も影響します。
さらに、度数の合わないメガネやコンタクトレンズの使用、ドライアイ、ストレスや全身の健康状態なども、目の不調を引き起こす一因となりえます。
休息しても取れない目の痛みやかすみは眼精疲労のサイン
一般的な疲れ目であれば、十分な休息や睡眠によって症状は回復します。
しかし、休憩しても目の痛みやかすみ、重い感覚が続く場合は眼精疲労の可能性があります。
眼精疲労は目だけの問題にとどまらず、慢性的な頭痛や肩こり、場合によっては吐き気といった全身の不調を伴うことも少なくありません。
これらの症状は、仕事のパフォーマンスや日常生活の質を著しく低下させる要因となりえます。
症状が長く続くようであれば、作業環境の調整や使用しているメガネの度数を見直すほか、専門医への相談を検討する必要があります。
長時間のデスクワークやスマホの使用が主な原因になる
デスクワークやスマートフォンの操作のように、近い距離にある対象物を長時間見続ける作業は、目のピントを合わせる筋肉を常に緊張させ、こわばりを引き起こします。
画面に集中するあまり、まばたきの回数が無意識のうちに減少し、涙の量が不足して目が乾燥しやすくなることも大きな原因です。
また、前かがみの姿勢は首や肩の血行を悪化させ、目への負担を増大させます。
不適切な室内の照明や、モニター画面のまぶしさ、度数が合っていないメガネやコンタクトレンズの使用も、目の疲れを助長する要因となります。
30分に一度は休憩を取り、姿勢や環境を整えることが予防の基本です。
仕事の合間にできる!眼精疲労を和らげるセルフケア方法

パソコン作業や会議などで画面を見続けると、ピント調節筋が硬直したり、まばたきの回数が減って目が乾燥したり、血行が悪くなったりします。
これらの要因が重なることで、目のかすみや乾燥感、重だるさといった不調が現れます。
重要なのは、作業の合間にこまめに目の緊張をほぐすことです。
30分に1〜2分程度でも、意識的に目を休ませる習慣をつけることで、午後の集中力や作業効率の維持が期待できます。
30分に1回は遠くを見て目の筋肉をリラックスさせる
目の周りの筋肉を動かしてストレッチすることは、目の疲れを改善し、気分をリフレッシュさせるのに役立ちます。
特に、近くの物を見る際に緊張する毛様体筋は、長時間同じ距離を見続けることで凝り固まり、疲れ目の原因となります。
意識的に窓の外の景色など、遠くをぼんやりと眺める時間を作りましょう。
遠くを見る行為は、緊張していた毛様体筋を弛緩させ、目の筋肉をリラックスした状態に戻す効果があります。
作業中に定期的にこの習慣を取り入れることで、筋肉の過度な緊張を防ぐことができます。
意識的にまばたきの回数を増やして目の乾燥を防ぐ
パソコン作業などで画面に集中していると、人は無意識にまばたきの回数が減ってしまいます。
まばたきは、涙を目の表面全体に行き渡らせて潤いを保ち、ほこりなどから目を守る重要な役割を担っています。
回数が減ると涙の蒸発が進み、目が乾いてドライアイの状態を招きかねません。
これを防ぐために、意識的にまばたきの回数を増やすように心がけましょう。
また、30分に数分程度の休憩を挟み、その間は目を閉じて休ませたり、コピーを取りに行くなど画面を見ない作業を行ったりすることも、目の負担を軽減する上で効果的です。
ホットタオルで目元を温めて血行を促進する
目元を温めることは、目の周りの血行を促進し、筋肉の緊張を和らげるのに有効です。
水で濡らしたタオルを固く絞り、電子レンジで40秒ほど(600Wの場合)加熱すれば、簡単に蒸しタオルが作れます。
これを目の上に乗せて数分間リラックスすることで、疲労の緩和が期待できます。
市販のホットアイマスクを利用するのも手軽な方法です。
目の周りには自律神経の切り替えに関わるスイッチがあるため、温めることで副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスした状態へ導きます。
ただし、目が充血して痛む場合は、温めるのではなく冷たいタオルで冷やす方が症状を和らげるのに適していることもあります。
目の周りのツボを押して緊張をほぐす
目の周りには、疲労回復に役立つとされるツボがいくつか存在します。
ツボは指で軽く押したときに、周囲より少しへこんでいるように感じられ、適度な圧痛がある場所が目安です。
例えば、目頭の少し上にある「晴明(せいめい)」や、眉頭の下にある「攅竹(さんちく)」、こめかみにある「太陽(たいよう)」などが知られています。
ツボを押す際は、指の腹を使い、気持ち良いと感じる程度の強さでゆっくりと圧をかけましょう。
左右同時に、皮膚をこすらないように押さえ、数秒間保持して離す動作を2〜3回繰り返すことで、目の周りの緊張を和らげる効果が期待できます。
肩や首を回す簡単なストレッチで血流を改善する
長時間同じ姿勢で画面を見続けると、肩や首周りの筋肉が硬直し、頭部への血流が悪化します。
この血行不良が、目の重さやだるさの一因となることがあります。
対策として、座ったままできる簡単なストレッチが有効です。
まず、背筋を伸ばした状態で両肩を耳に近づけるように引き上げ、そこから大きく後ろに向かって10回ほど回します。
同様に前回しも10回行いましょう。
次に、首をゆっくりと左右、前後に倒し、それぞれ10秒ほど筋肉が伸びるのを感じながら静止します。
このとき、反動をつけないように注意が必要です。
これらの動きで首から肩にかけての筋肉がほぐれ、血流が改善し、目の疲れの軽減につながります。
眼精疲労におすすめのセルフケアアイテム
日々のセルフケアに便利なアイテムを取り入れると、眼精疲労の主な要因である「乾燥・こわばり・血行不良」に、より効率的に対処できます。
例えば、目元を温めて血行を促すホットアイマスク、目の乾きを手軽に潤す防腐剤無添加の人工涙液、まぶしさや反射を抑えるデスクライトなどが代表的です。
時間帯に応じて使い分けるのも良い方法で、例えば午前中は潤いケア、昼休憩には温めとピントのリセット、一日の終わりにはストレッチと温めを組み合わせるなど、自分の状態に合わせて活用しましょう。
ホームワック ピントフレッシュで目の状態を整える
「ホームワックピントフレッシュ」は、近くを見続けることで固まってしまった目のピント調節筋をほぐすための補助的なツールです。
内部のレンズがクリアな状態とぼやけた状態を交互に作り出すことで、目の筋肉に柔軟な動きを促し、ピントが合いやすい状態へと導きます。
1回の使用時間は3~5分程度が目安で、作業の合間の短い休憩時間に取り入れるのが効果的です。
特に、デスクワークが多く夕方になるとピントが合いにくくなるような場合に、こまめなリセットとして役立ちます。
メガネやコンタクトレンズの見直しで眼精疲労を軽減する

眼精疲労の意外な原因として、日常的に使用しているメガネやコンタクトレンズが合っていないケースが挙げられます。
度数が強すぎたり弱すぎたりすると、目はピントを合わせるために余計な力を使い、結果として疲れやすくなります。
特に、長時間のデスクワークなど、特定の距離を見続けることが多い場合は、その作業環境に合わせた度数調整が重要です。
定期的に視力検査を受け、自分の目の状態やライフスタイルに最適な視力矯正を行うことが、眼精疲労の予防と軽減につながります。
度数が合っていないメガネやコンタクトは疲れの原因になる
自分の視力に合っていない度数のメガネやコンタクトレンズを使い続けると、目は常に無理な力を使ってピントを合わせようとするため、ピント調節筋に過剰な負担がかかります。
また、乱視が矯正されていなかったり、レンズの中心と瞳孔の位置がずれていたりすることも、かすみや頭痛、肩こりを引き起こす原因となります。
特にデスクワークが中心の生活であれば、遠くまで見えることだけを重視した度数ではなく、パソコン画面などの作業距離に最適化した「中近レンズ」や「近々レンズ」を選ぶ方が快適な場合があります。
夕方になると特に疲れを感じるなど、見え方に違和感がある場合は、半年に1回を目安に視力と度数のチェックを受けることを推奨します。
ブルーライトカット機能付きのメガネを活用する
ブルーライトカット機能付きのメガネは、LEDディスプレイから発せられる光のまぶしさや散乱を軽減する効果が期待できます。
これにより、画面のコントラストがはっきりし、文字などが認識しやすくなることで、目の不快感が和らぐ場合があります。
製品によってブルーライトのカット率が異なり、カット率が高いものは視界が黄色みがかって見えることがあるため、色味の変化が少ない自然な見え方のものから試すのがよいでしょう。
ただし、メガネだけに頼るのではなく、モニターの明るさを室内の照明環境に合わせたり、画面への映り込みを防ぐように配置を工夫したりするなど、光環境全体を見直すことがより効果的です。
目の乾きを抑える保湿成分配合のコンタクトレンズを選ぶ
コンタクトレンズ装用中の目の乾燥感は、眼精疲労の大きな要因です。
この対策として、レンズ素材に保湿成分が配合されていたり、レンズ表面の水分を保持する技術が用いられたりしている製品を選ぶと、乾燥感を軽減しやすくなります。
また、酸素をよく通すシリコーンハイドロゲル素材のレンズや、毎日新しいものに交換するため汚れが蓄積しにくいワンデータイプのレンズも、快適な装用感を保つ上での選択肢となります。
定められた装用時間を守り、乾燥が気になる際は防腐剤が含まれていない人工涙液を併用することも有効です。
自分の目に合っているか、ベースカーブなどを専門店や眼科で定期的に確認しましょう。
市販の目薬や医薬品を使った眼精疲労の対処法

市販されている目薬や医薬品を上手に活用することで、眼精疲労に伴う不快な症状を一時的に和らげることが可能です。
選ぶ際は、自分の症状に合った製品を見極めることが重要です。
例えば、ピントが合いにくいと感じるならピント調節機能をサポートする成分が入ったもの、目の乾きが気になるなら涙に近い成分の人工涙液、目の疲れと共に全身のだるさも感じるならビタミン剤などの内服薬が選択肢になります。
製品の用法・用量を守り、セルフケアと併用して目の負担を減らしましょう。
ピント調節機能を改善する成分が入った目薬を選ぶ
長時間のデスクワークなどで近くを見続けた後、「夕方になるとピントが合いにくくなる」「一時的に視界がぼやける」といった症状がある場合、ピント調節筋が凝り固まっている可能性があります。
このような症状には、硬直したピント調節筋(毛様体筋)の働きを助ける成分、例えばネオスチグミンメチル硫酸塩などが配合された目薬が適しています。
製品のパッケージに「眼精疲労」「ピント調節機能改善」といった記載があるものを選ぶとよいでしょう。
まずは清涼感が強すぎない、マイルドな使用感のものから試すのがおすすめです。
緑内障の治療中の方や妊娠・授乳中の方は、自己判断での使用は避け、事前に医師や薬剤師に相談してください。
ドライアイには涙に近い成分の人工涙液を使用する
パソコン作業に集中するとまばたきの回数が減り、目が乾燥して異物感やしょぼしょぼした感覚が生じやすくなります。
このようなドライアイの症状には、涙の成分に近い人工涙液タイプの目薬が有効です。
涙液不足を補い、目の表面に潤いを与えることで、乾燥による不快感を和らげます。
頻繁に点眼する場合は、角膜への影響を考慮し、防腐剤が含まれていない使い切りタイプの製品を選ぶとより安心です。
コンタクトレンズを装用している場合は、パッケージに「コンタクトレンズをしたまま点眼可能」といった表示がある製品を使用しましょう。
強い清涼感のあるタイプは、かえって目に刺激を与えることもあるため注意が必要です。
ビタミン剤などの内服薬で体の中からアプローチする
目の疲れだけでなく、肩こりや腰痛といった全身の不調も伴う眼精疲労には、ビタミン剤などの内服薬で体の中からケアする方法もあります。
特に、ビタミンB群(B1、B6、B12)は、目の周りの筋肉や神経のエネルギー代謝をサポートし、疲労回復を助ける働きがあるとされています。
目薬のような即効性は期待できませんが、睡眠や姿勢の改善、作業環境の見直しといったセルフケアと並行して継続的に摂取することで、疲れにくい体作りを支えます。
すでに他の薬を服用している場合や持病がある方は、飲み合わせに問題がないか、購入前に薬剤師に相談することをおすすめします。
眼精疲労を予防するための生活習慣と作業環境

眼精疲労を予防するためには、日々の生活習慣や作業環境を整えることが非常に重要です。
目の負担は、「見る距離」「光の環境」「室内の湿度」「体の回復」という4つの要素を見直すことで大幅に軽減できます。
具体的には、モニターと目の距離を適切に保ち、画面の明るさを部屋の照明に合わせて調整し、映り込みをなくすこと。
そして、加湿器で適度な湿度を保ち、十分な睡眠で目と自律神経を休ませることです。
これらの基本的な対策を習慣にすることが、疲れの蓄積を防ぐ鍵となります。
パソコンモニターと目の距離を40cm以上保つ
パソコンで作業する際は、モニター画面と目の間に少なくとも40cm以上の距離を確保することが推奨されます。
画面が近すぎると、目のピントを合わせる筋肉に常に強い負荷がかかり、眼精疲労の直接的な原因となります。
椅子や机の高さを調整して正しい姿勢を保ち、背筋を伸ばした状態で楽に画面が見える位置を探しましょう。
この距離で文字が見えにくい場合は、無理に目を凝らすのではなく、作業距離に合わせた適切な度数のメガネを使用することも検討すべきです。
また、画面の位置を少し見下ろす角度に設定すると、目の露出面積が減り、涙の蒸発を抑えて乾燥を防ぐ効果も期待できます。
部屋の明るさを調整してモニターの反射を抑える
作業空間の照明環境は、目の疲れに大きく影響します。
部屋が明るすぎたり暗すぎたり、モニター画面の輝度との差が大きかったりすると、目の負担が増加します。
理想的なのは、手元の書類やキーボードの上が300ルクス以上、ディスプレイ画面の明るさが500ルクス以下になるように調整することです。
また、天井の照明や窓からの光が画面に映り込む「グレア」は、コントラストを低下させて非常に目を疲れさせます。
ブラインドやカーテンを利用して直射日光を遮ったり、モニターの角度や向きを変えたりして、画面への映り込みをなくす工夫が必要です。
非光沢タイプのモニターを選ぶことも有効な対策の一つです。
加湿器を使い室内の湿度を適切に保つ
空気が乾燥していると、目の表面から涙が蒸発しやすくなり、ドライアイや眼精疲労を引き起こす原因となります。
特に、夏や冬にエアコンを使用する室内は乾燥しがちです。
加湿器を設置して、室内の湿度を40%から60%程度に保つように心がけましょう。
これにより、目の表面の潤いが維持され、乾燥による不快感を軽減できます。
また、エアコンの送風が直接顔や目に当たらないように、風向きを調整することも大切です。
作業の合間に意識的にまばたきの回数を増やしたり、温かい蒸しタオルで目元を保湿したりすることも、乾燥対策として効果があります。
十分な睡眠時間を確保して目をしっかり休ませる
日中に酷使した目の筋肉や神経を回復させるためには、質の良い睡眠が不可欠です。
睡眠中には、目の組織が修復され、日中の活動で溜まった疲労物質が排出されます。
睡眠時間が不足すると、目の回復が追いつかず、疲れが翌日に持ち越されて眼精疲労が慢性化する原因にもなります。
心身をリラックスさせるためにも、毎日十分な睡眠時間を確保するよう努めましょう。
また、過労や精神的なストレスも目の不調につながるため、適度な休息を取り入れ、軽いストレッチなどで体の緊張をほぐすことも、質の高い睡眠と目の健康維持に役立ちます。
食生活の改善によって眼精疲労になりにくい体を作る

眼精疲労の対策として、食生活の見直しも有効なアプローチの一つです。
特定の栄養素だけを偏って摂取するのではなく、主食、主菜、副菜のそろったバランスの良い食事を基本とすることが重要です。
その上で、目の健康維持に役立つとされるビタミンAやビタミンB群、アントシアニンといった栄養素を意識的に食事に取り入れることで、疲れにくい体作りをサポートします。
日々の食事から、目の機能を内側から支える習慣をつけましょう。
目の健康維持に役立つビタミンAを多く含む食品
ビタミンAは網膜で光を感知する「ロドプシン」の生成に関わるほか、目の粘膜を健康に保ち、表面の潤いを維持する働きがあります。
この栄養素が不足すると、暗い場所での見え方が悪くなることがあります。
ビタミンAは、うなぎ、レバー、卵などに含まれる「レチノール」と、にんじん、かぼちゃ、ほうれん草といった緑黄色野菜に多く含まれ、体内でビタミンAに変換される「β-カロテン」の形で摂取できます。
β-カロテンは油と一緒に摂ることで吸収率が向上するため、炒め物やオイルを使ったドレッシングで和えるなどの調理法がおすすめです。
血行を良くするビタミンEが豊富なナッツや魚介類
ビタミンEには強い抗酸化作用があり、細胞の酸化を防ぐと共に、末梢血管の血流を促進する働きがあります。
目の周りの血行が良くなることで、筋肉や神経に必要な酸素と栄養素が効率的に供給され、疲労の蓄積を和らげる効果が期待できます。
ビタミンEは、アーモンドやヘーゼルナッツなどのナッツ類、アボカド、植物油に豊富です。
また、さんま、いわし、さけなどの魚介類からも摂取することが可能です。
おやつに一掴みのナッツを取り入れたり、週に数回は魚料理を食卓に加えたりすることで、継続的に摂取するとよいでしょう。
目の働きを助けるアントシアニンを含むブルーベリー
アントシアニンは、ブルーベリーなどに含まれる紫色の色素成分で、ポリフェノールの一種です。
この成分は、網膜で光を感じるために働くロドプシンという物質の再合成を助ける作用が報告されており、目のピント調節機能をサポートし、一時的な目の疲労感を和らげる効果が期待されています。
アントシアニンはブルーベリーのほか、カシスやなす、黒豆などにも含まれています。
冷凍のブルーベリーをヨーグルトやシリアルのトッピングとして加えるなど、日常の食事に手軽に取り入れることが可能です。
食事はあくまで健康の土台であるため、作業環境の見直しや十分な休息と併せて対策しましょう。
セルフケアで改善しない場合は眼科で専門医に相談しよう

これまで紹介したセルフケアや環境改善を数日から1週間程度試しても、目の痛みやかすみ、強い乾き、頭痛といった症状が続く場合は、自己判断で対処を続けるのではなく、眼科を受診することをお勧めします。
特に、急に視力が低下した、光が普段よりまぶしく感じる、片目だけ見え方がおかしい、物が二重に見えるといった症状は、別の病気が隠れているサインかもしれません。
専門医による正確な診断を受けることが、根本的な原因の特定と適切な治療への第一歩となります。
眼科の検査で隠れた目の病気がないか確認する
眼科では、まず視力検査、眼圧測定、屈折検査などを行い、目の基本的な状態を確認します。
その後、細隙灯顕微鏡という装置を使って角膜や結膜に傷や炎症がないか、水晶体に濁りがないかなどを詳細に観察します。
これらの検査により、眼精疲労の背景にドライアイ、角膜障害、緑内障、白内障といった治療が必要な病気が隠れていないかを調べることが可能です。
また、涙の量を測る検査や、目のピント調節機能の検査、場合によっては眼底検査も行い、症状の原因を多角的に探ります。
自覚症状だけではわからない問題を明らかにすることが、的確な対策につながります。
処方箋で出される目薬や内服薬による治療を受ける
眼科での診察の結果、ドライアイやアレルギー、炎症など、特定の原因が診断された場合は、それに応じた治療薬が処方されます。
例えば、涙の分泌を促したり、角膜の傷の修復を助けたりする点眼薬、炎症を抑える点眼薬など、市販薬よりも専門的な効果を持つ薬剤による治療が可能です。
また、目のピント調節筋の緊張を和らげる目的の点眼薬や、ビタミンB群などの内服薬が処方されることもあります。
医師の指示に従って正しく薬を使用し、定期的に通院してその効果を確認しながら、症状の改善を目指していきます。
まとめ
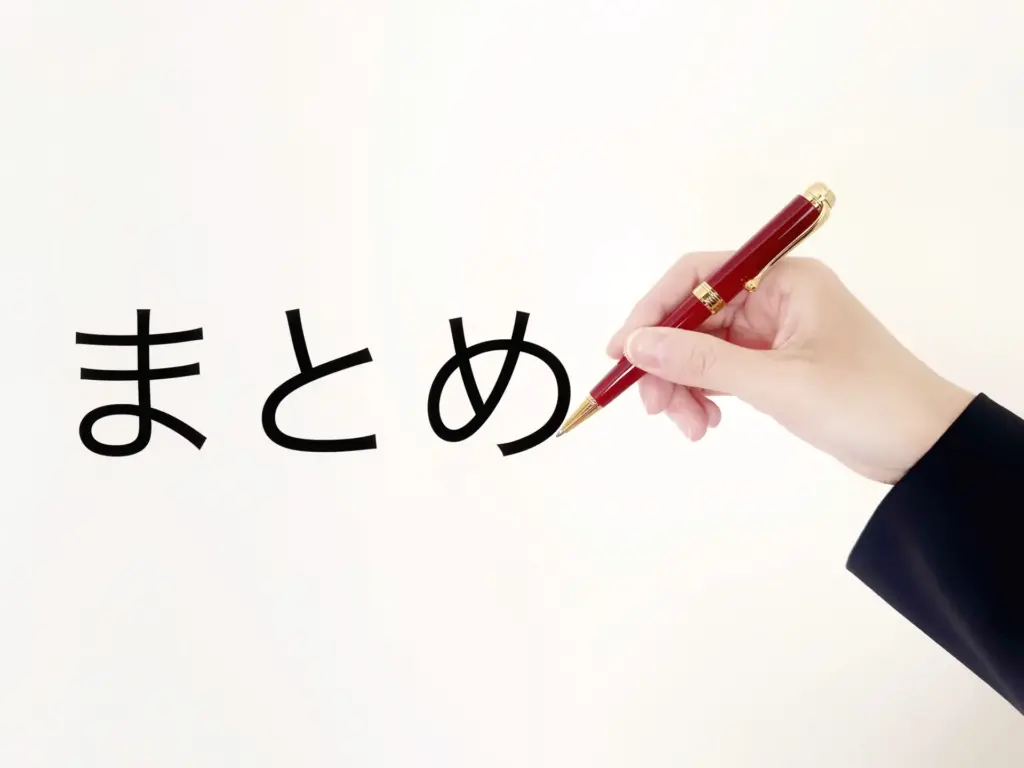
眼精疲労は様々な要因が絡み合って生じるため、一つの対策に頼るのではなく、多角的なアプローチが有効です。
日々の生活では、作業環境を整え、セルフケアでこまめに目をリフレッシュさせることが基本となります。
症状が改善しない場合は、自分の視力や生活スタイルに合ったメガネやコンタクトレンズへの見直しを検討しましょう。
また、目の乾きやピントの合いにくさといった症状に応じて、適切な成分を含む目薬を活用するのも一つの手段です。
さらに、目の健康を支える栄養素を意識した食事を心がけ、体の中からコンディションを整えることも予防に役立ちます。
これらの対策を組み合わせても不調が続く際は、自己判断せず専門医に相談してください。











